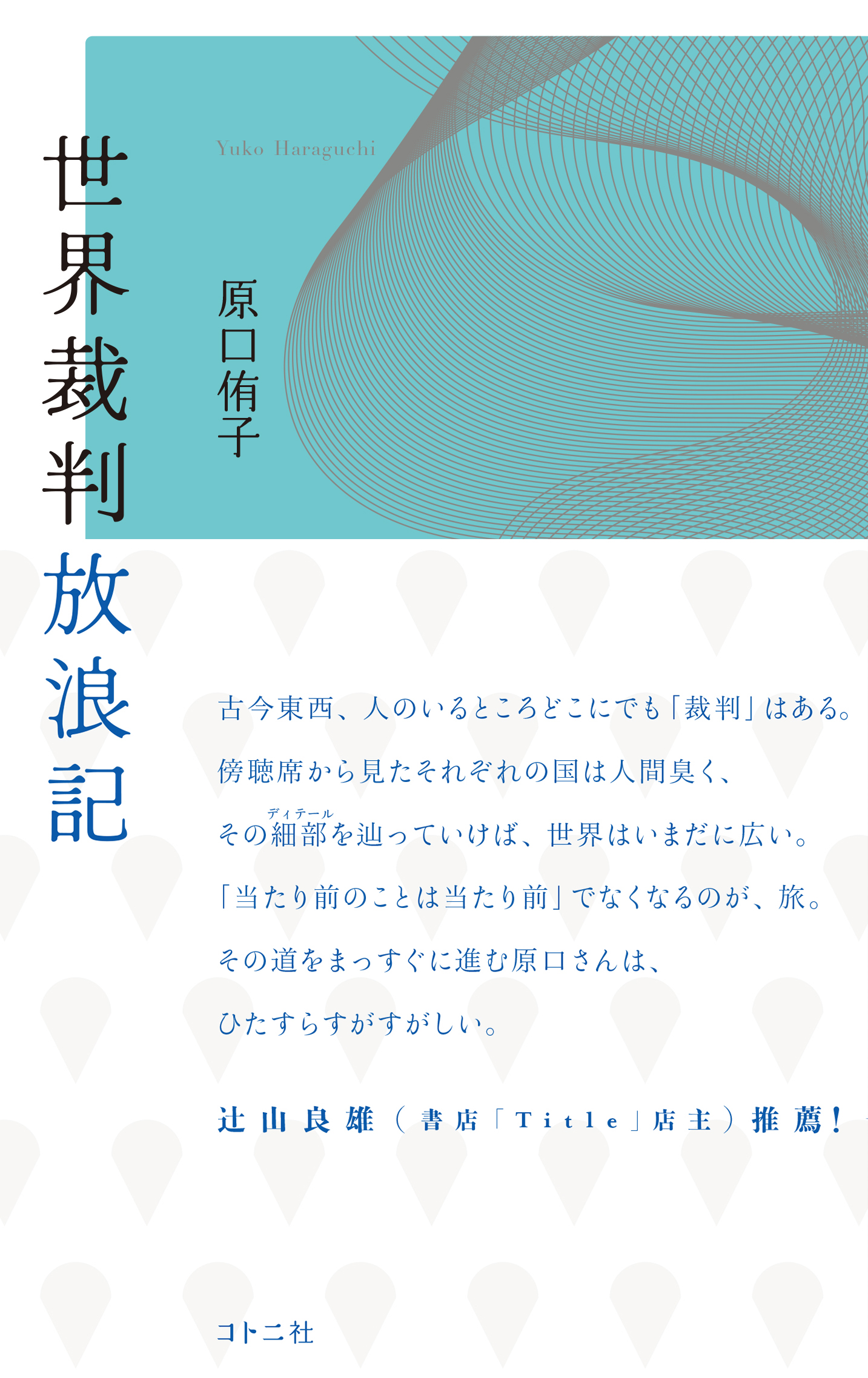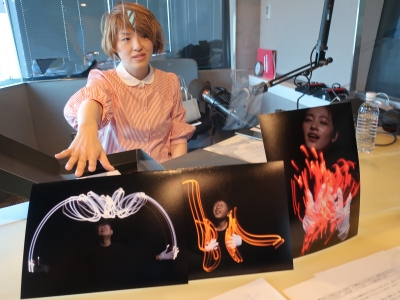2022年05月04日
世界の反応、国それぞれ…というお話伺います。
マイム・アーティストのが〜まるちょば、
HIRO-PONさんをお迎えしています。
海外で35ヵ国、200以上のフェスティバルに
招待されて出演されてきたが〜まるちょば。
実際のフェスティバルで感じた日本の観客との
違いとは?
HIRO-PON「お客さん自体は自己表現が上手です。
日本の方は良くも悪くも、周りの状況を踏まえて
自分を表現するので。欧米の人たちは自分が
面白いと思ったら気にせずに笑うし、手を叩いて
くれます。自己表現を自分の意思でやるのが
海外の人たちなんです。面白くなかったら人の
前でも勝手に帰って行く人もいたり…」
小黒「そういう海外のフェスティバルで
国ごとの工夫があったりするんですか?」
HIRO-PON「たとえば“お金“のジェスチャーが
違ったりするんです。日本だとOKマークで
お金ってわかるけど、海外では全く違う意味が
あったり…そういう動きが出てくる場合はそれを
変えたり、宗教的にダメな物は変えたり…
基本的には、人に訴えるものは変えたりして
いないので、ジェスチャーは変えても内容は
変えずにしています。」
今までの海外公演の中で、一番印象的な喜び方を
したのはスペインの観客。しかし、その喜び方は
HIRO-PONさん曰く大味だったとか…
演劇に対する理解は深いかもしれないですけど、
見方が違うと言いますか…スペインの出演者
と話した時も『Aの笑いが収まる前に、Bの
笑いを出そう』っていう話をしていると、
『お前たちはそんなところまで考えているのか』
って言われたりするんです。
その時楽しければいいみたいな…本当、大味
何ですよね」
▼が〜まるちょば公式サイト
http://www.gamarjobat.com
▼が~まるちょば LIVE 2021-2022 STORIES
『PLEASE PLEASE MIME』
5月19日、20日は渋谷区総合文化センター大和田でLIVEもあります。
↓↓詳しくは↓↓
http://www.gamarjobat.com/jp/topics/detail/2814
今夜の選曲…Twist and Shout / BEATLES