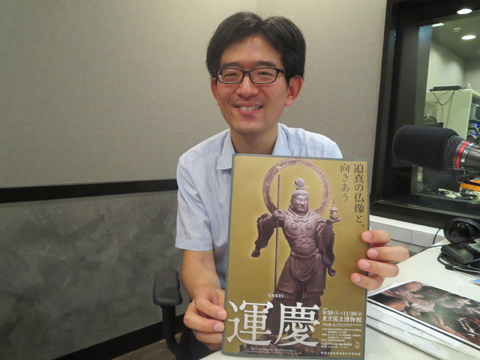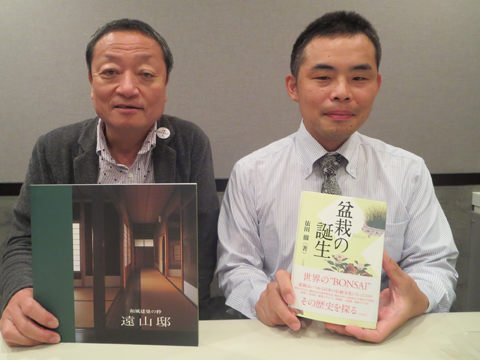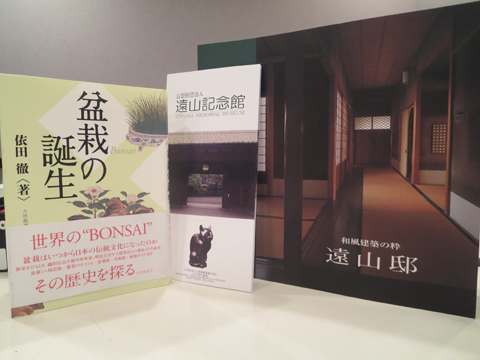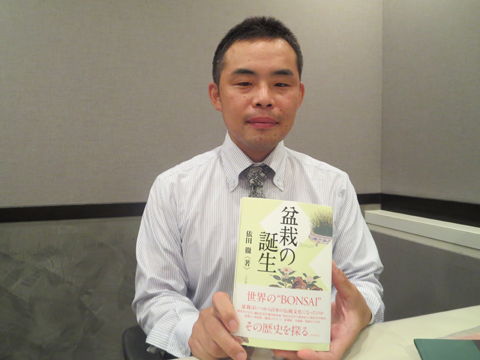2017年09月07日
最新技術で見える仏像の謎。 天才仏師 運慶が残した痕跡とは?
東京国立博物館 研究員 西木政統さんをお迎えしています。

近年の運慶作品の研究では、X戦で用いて
調査されているとお聞きしますが、
最近の発見ではどんなものがあった?
西木さん「仏像というのは平安時代以降、
軽くするため、あるいは作業を行いやすくするために
いくつもの部品に分けてくり抜いた状態から
接合していくんですね。接合後、くり抜いた後の空間に
お経を書いた板ですねとか、あるいは仏像を
作らせた方の大事なものを収めるといったことするんです。
なので運慶の仏像に限らず、X線を通してみる中に
何が入っているか確認することができるんですね。
その中でも運慶の作品には、お経が書かれた独特な板が
よく収められているということがわかってきたんですね。
そうしますと、運慶風の仏像でも中に板が入っていれば、
運慶の可能性が強まっていくということになるんですね。
普段は、なかなかX線にかけるというのは、
仏像を運ぶ必要もありますし、時間もかかるということで
気軽に行うことが難しいんですね。ただ今回は、
展覧会で実際に仏様をお借りできますので、会期中でも
随時調査を致しまして、何か新しいことがわかったら、
展覧中にもどんどん発表して盛り上げていきたいと思います。」
==================================
興福寺中金堂再建記念特別展「運慶」
会期:9月26日(火)ー11月26日(日)
会場:東京国立博物館
休館日:月曜日(10月9日(祝)は開館)
時間:午前9時30分〜午後5時
==================================
今夜の選曲:WALK DON'T RUN / PENGUIN CAFE ORCHESTRA